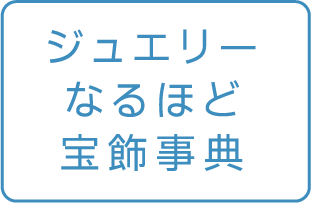真珠の宝石言葉 健康、長寿、富
日本では、「しらたま」という名で呼ばれていた真珠はダイヤモンドよりはるかに古い歴史を誇り、高貴な人々のステータスとして君臨していたようです。
パールには悲しみを喜びに変える力があるとされ、女性らしさ、気品、優雅、芸術的なセンスを増強してくれる石だと言われています。
宝石を愛したエジプトの女王、クレオパトラも真珠の不思議な魔力に吸い寄せられたひとりで美しさに磨きをかけるために、真珠を粉にして飲み干したという贅沢なエピソードがあります。

種類と特徴
色は、ピンク・グレー・ホワイト・グリーン・ゴールド・クリーム・ゴールド・ブルーなどがあります。
南洋真珠・・・白蝶真珠とも言われる南洋真珠の産地はオーストラリア、フィリピンがあげられ、最大で16mmupのものがあり、色はピンク・グレー・クリームなどがあり、中でもピンク色のでるものは稀少性が高いと言われています。
黒蝶真珠・・・産地はタヒチ、パナマ、奄美で、色はブラック、ブルー、シルバー等があります。
品質は色合いにより、ピーコックグリーン・グリーン・ライトグリーン・ブラック・ブルー・シルバーがあります。
真珠の中でも神秘的な色合い、稀少性から真珠の女王と言われています。
他にもマベ真珠・淡水真珠・ベビーパール・バロックなど真珠の品種は多彩です。
◆ マーガリンと真珠 ◆
喜連川宝石研究所 所長 喜連川純氏著
人の親ともなれば、誰しもわが子にいい名前をつけたいと思うのが人情。
それが女の子なら、なおさら可愛く美しい子に育ってほしいと、願いを込めて名前をつけるのが親心というものでしょう。
この気持ちは洋の東西を問わず変わらないと思います。
そこで、欧米で多くつけられている名前がギリシャ語のマーガライト(真珠)からきたマーガレット、マルガレーテ、マルゲリータ、マルグリットなど、美しいものの象徴である真珠に由来した名前です。
日本では、さすがに「真珠」という、そのものずばりの名前は見かけませんが、「珠美(たまみ)」という名が、さしずめ、欧米のそれに近い名前というところでしょうか。
真珠の美しさは、人の名ばかりではなく、その清純さと愛らしさから、花の名前にもつけられています。
そうです。
皆様ご存じのカナリア諸島原産の、真珠のように白い花「マーガレット」がそれです。
さらに食品でも、真珠のような肌と色を連想させるところから、バターの代用品に「マーガリン」という名がつけられました。
マーガリンは、1869年(明治2年)にナポレオン3世の人造バター製造の懸賞募集に応じたフランス人メージュ・ムーリエによって発明されたもので、最初はいまのように着色されておらず、真っ白の乳化物だったのです。
◆ 真珠の肌と美しさの秘密 ◆
さて、その美しい肌と、真珠特有の干渉色はどのような物質ででき、どんな構造になっているのでしょう。
真珠ができるためには、貝に不可欠な条件があります。
それは内面がアワビみたいに美しい貝殻でなくてはならないことです。
蛤(はまぐり)とかあさりでは真珠をつくりことができません。
真珠をつくる貝殻の断面は、建築物の断面によく似ています。
つまり、ビルならタイル、コンクリート、内装となりますが、貝は外側の殻皮、コンクリートにあたる稜柱層(りょうちゅうそう)、奇麗な内装である真珠層からできています。
この真珠層が真珠になるわけで、内装部のない蛤みたいな会はログハウスのようなもの、たとえ珠をつくったとしても、腎臓結石か胆石みたいなものしかできないのです。
内装である真珠層の材料はアラゴナイトという炭酸カルシウムでできています。
ここで、ディスコなどで見られるミラーボールを思いうかべてください。
あれは、ちいさい鏡を球体前面に張り詰めておりますが、真珠は貝殻でつくった核という球体に、透明で、チョー薄く小さいアラゴナイトの板状結晶を、コンキオリンというタンパク質でできた接着剤で覆いながらできたものです。
ただ、ミラーボールはひと巻きですが、真珠は、アコヤ貝でも、ゆうに千巻きもタマネギ状の層になって巻いております。
このアラゴナイト1枚の厚みがアコヤ貝で0.24~0.5ミクロン。
南洋真珠でしられているシロチョウガイなら、0.3~0.6ミクロンという薄さです。
このぐらいの薄さになりますと数字では分かったゆな気になっても、実際にはどのぐらいの厚さなのか見当もつきません。
そこでいろいろ考えたところ、ありました。
いま市販されているビン詰めの金箔、あの一枚が0.3ミクロンで、この金箔の一枚から二枚がほぼ真珠層一枚分の厚さになるのです。
これが千層以上も重なり、その層に光があたったとき、あの美しい真珠光沢と複雑な干渉色が生まれてくるというわけです。
◆ 真珠の美しさはどのくらいもつのでしょうか ◆
海にかこまれた日本は、古代から真珠の生産地でした。
万葉集の中にも白珠(しらたま)とか鰒珠(あわびだま)という言葉がよくでてきます。
銚子の漁師さんに聞いた話ですが、一年に一個か二個、あわびから天然真珠がでてくるそうです。
現在、あわびの養殖真珠は五島列島の小値賀(おじか)島で少量つくっています。
あわびの貝殻は正倉院の螺鈿(らでん)でつくった御物(ぎょぶつ)にも使われておりますが、他の螺鈿材であるさざえや夜光貝ともども、いまだに美しく輝いております。
◆ 真珠とは、貝の体内にできた貝殻である ◆
これが真珠の定義です。
ということは、さきほどの千数百年たった螺鈿の貝と真珠はまったく同じ材質ですから、使った後のお手入れと保管さえよければ、おなじように千年二千年と美しさが保てるわけです。
そうそう、奈良の正倉院展に行かれたときは、ぜひ、大仏さまの裏にある三月堂に行かれることをおすすめします。
ここには不空羂索観音(ふくうけんじゃくかんのん、733年)がまつられていますが、この観音さまの頭上には、真珠、水晶、めのうなど二万余個の宝石でつくられた直径六十センチもある宝冠が飾られております。
また、お顔の眉間(みけん)にある白毫(びゃくごう)も、あわびの真珠でつくられております。
ただ、像の高さが三メートル六十二センチもありますし、暗いので、できればペンライトとオペラグラスを持っていかれるとよろしいでしょう。