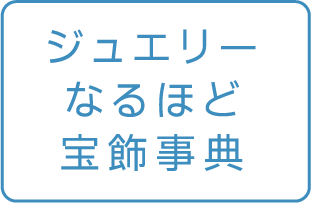オパールの宝石言葉 希望・幸福
楽しく、こころ和む宝石オパール
オパール最大の魅力は一つひとつが全く違う美しさを持っていることです。

語源
オパールは貴石を意味するラテン語の「オパルス」に由来しています。
オパールの種類
①ライトオパール
②ブラックオパール
③ファイヤーオパール
④ボルダーオパール
産地
現在オーストラリアが世界産出量の約90%を占めています。
ライトオパールとブラックオパールは、サウスオーストラリア州。
ボルダーオパールは、クィーンズランド州。
ファイヤーオパールは、メキシコです。
色の種類
オパールの色は、遊色効果の何色が強いのか、貴重なのかが議論されます。
最高がレッド、オレンジ、グリーン、ブルーの順に評価が高いと言われています。
色の輝き
色の強さ、全体の鮮やかな冴えが良いオパールの必要条件です。
この鮮やかさをオパールの色の輝きと表現します。
◆ オパールは眼の特効薬? ◆
喜連川宝石研究所 所長 喜連川純氏著
地球がつくった「無機質の虹色ゼリー」。
十月の守護石オパールは、わたしたち日本人のもっとも好きな宝石の一つです。
オパールとはドイツ語の読み方で、フランスならたんにオパル、英語ではオゥパルといいます。
オパールをこんにちのように、世界のどなたにでも求めることができるようになっだのは、
メキシコやオーストラリアで発見発掘されるようになった明治以降になってからのこと。
それまでは、もっぱら古代ローマから明治の時代まで、東欧の、いまはスロバキア領になっているチェルウエニッツア(ブタペストの北東二百三十㎞にあるプレショフから北に十㎞付近)のハンガリアンーオパールだけが唯一の供給源でした。
しかし、ここの鉱床も十九世紀末までにはほぼ掘り尽くされ、廃坑同然となってしまいました。
このハンガリアン・オパール全盛時の中世ヨーロッパでは、オパールは美しいから身に着けるというだけでなく、「眼に特別な威力をもつ宝石」だと信じられ使われていました。
その一つは、持っている人の眼の病を直し、もう一つは、持ち主の姿を隠すことができる、
つまり、忍者みたいな力をもつ宝石だと思われていたのです。
そのために盗人にとっては好都合の石ということで、別名「盗賊のパトロン」ともよばれていました。
本当にそのことを信じて泥棒が身に着けて入ったとすると、その仕草を想像しただけで、笑いがこみあげてきます。
因みにメキシコで本格的に採掘がはじまったのが一八七〇年(明治三年)。
みなさんご存じのオーストラリア・オパールも一八七五年(明治八年)のクイーンズランド州の発見が記録に残ったものとしては最初です。
◆ 見ていて飽きのこない色の変化 ◆
いったい、オパールはどんな物質でできているのでしょうか。
オパールは二酸化ケイ素(シリカ)に水が加わったもの(ケイ酸といいます)でできていて、ご存じの乾燥剤シリカゲルと兄弟みたいな関係の物質です。
オパールを約一万倍の電子顕微鏡で見てみますと、イクラやたらこのような球状の粒が規則正しく集まってできていることがわかります。
ただ、この粒の大きさは、オパールの赤い色がでるいちぱん大きい粒の直径でも○・ニミクロン、つまりこの粒をすらっと一列に干個並ぺてやっと○・ニミリにしかならないおおきさです。
オパールは、こんな小さな粒が、パチンコの玉のブロック、イクラの粒のブロック、たらこ、数の子の粒といった具合に、いろいろなおおきさの粒のブロックが集合してできたものといえます。
しかし、粒の大きさが○・○ハミクロンという小ささになると、オパールをどのように回転しても紫色しかでてきません。
さて、あのいつまで見ていても飽きのこない美しい色は、どのような仕組みででてくるのでしょうか。
ちょっとパチンコの玉を想像してみてください。
玉を箱いっぱい入れ、左右に揺すると、玉は安定したおさまり方をしますが、球体ですので、当然、そこには規則正しいすきまができてきます。
オパールに入った光は、このすきまを通り、回折(光が物体でさえぎられたとき、なおも物体の背後に回り込む現象)したり、粒々にぶつかって乱反射したりして、シャボン玉のような干渉色をだします。
一方、人間の眼に見える光の波長は赤がいちばん長く、だんだんと撥、黄、緑、青、藍、紫と短くなり、これ以下の短い波長は紫外線みたいに眼に見えない光になってしまいます。
さきほどのすきまを回り込んできた光は、となりの回り込んできた光と干渉し、美しい干渉色をつくりだしますが、この回折現象は、隣り合った空洞との距離に関係があり、ケイ酸球が大きくなると空洞と空洞の距離も長くなりますので長い波長の赤が見え、小さい粒なら空洞の距離も短く、短い波長の色しかでてきません。
このように球の大きさがオパールの色をきめているわけです。
赤がでるということは、それ以下の波長の紫まででてくるということになり、小さな粒なら、赤はでないで、青とか緑以下の色しか楽しむことができないということになります
オパールは赤斑(ふ)がでてご二色以上たのしめるものが高価で、藍とか紫しか見ることができないオパールは低品質品であるという理由がお分かり頂けたでしょうか。
◆ 大切なオパールをこわさないために ◆
沢地久枝さんの「遊色」という本にこんなくだりがあります。
「プレイング・オブ・カラー(ほんとはプレー・オブ・カラー)を遊色と訳したのは誰なのでしょう。
オパールの別名です(うそ)。
その結晶のなかに炎をもち、光の具合でさまざまに色がかわることからつけられた名前です。
そして、ときどき水をやらないと割れて(とんでもない)しまうのだそうです。」
たしかに宝石質のオパールは六~一〇%水分を含んでいますが、植木と違って水をやっても水分を吸収することはありません。
むしろ塩魚の塩分を抜くとき、塩水を使って塩抜きをするように、オパールを水に浸けたり出したりすると、かえってオパールの水分を引き出してしまう結果になります。
保存にはグリセリンを薬局でお求めになり、これで汚れを取ったり拭いたりしてください。
グリセリンの膜は、適度な保湿性をもち、オパールの乾燥をふせいでくれますので、ヒビ割れの予防になります。
ただ、オパール全体を被膜で覆うように拭いてください。
せっかくIセンチできるのに五百万年もかかって、しかも、いい形に磨きあげるため、それを削ってけずって、やっとお客様のものとなっだのですから、大切にお使いいただきたいものです。
また、オパールは硬度五・五~六・五と軟らかいので、お出掛けになるときだけお楽しみください。